

|
|
話す能力は 遺伝 |
数の読み方の 不思議 |
考えてみよう 言葉のこと。 |
宇宙の構造を解きあかす命波理論 --望遠鏡と顕微鏡と天鏡-- |
日の本大和 (ヒノモトヤマト) |
命波(めいは)とは何か |
命波(めいは)を 学ぶにあたって |

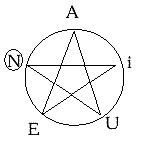
|
ことばは命だった! |
|
「ことば」という音を聞いた時あなたの脳裡にはどの文字が浮かびますか?
透明な光のバイブレーション(波動=エネルギー)とは何でしょうか? 小田野先生はこうやって何だろう何だろうと問い続けて終に生命とは「光透波」だったと気づき、それを証明する方式を考案し、宇宙の真理と森羅万象の謎を解明する「鍵」とも暗号解読法ともいえる「天の鏡図」を完成されたのです。 小田野早秧という人 初めて田園調布のお宅にお伺いしたのが1996 年の4 月のことで、以来3 年余り毎週のようにお伺いさせていただいている。 始めはお話を聞いているうちに耐えられないほどの眠気を催し、覚めているのが拷問に近い苦痛だった。座っているのも苦痛で、30 分もたつと横になりたくなる。幸い(?)腰を痛めたので、それを口実に横にならせていただいてお話を聞くという失礼を平気でしていた。 お会いする度に少しずつ己の身勝手さ、失礼さ、ごう慢さ、怠惰さ、粗雑さが先生という明鏡にそのまま映し出されているのが見えてくるようになった。あるとき初めてそのことに「あっ」と気づいてどっと冷や汗をかいた際先生がじっと私を見つめていらっしゃるのに気づいた。その時である、先生の両眼から小さなおもちゃの兵隊さんがヤットコヤットコくり出して来て、私の眼の中に陸続と入ってきた。愛情という兵隊さんで胸が満ちあふれ涙をこらえるのに懸命だった。 そ れ以来人生がまるで変わってしまった。真の愛の片鱗を味あわせていただいたのである。それは少しも重苦しくなく、めそめそとセンチメンタルでもなくて理性に裏打ちされた厳しく潔いものであった。甘やかされているのでなく鍛えれらている歓びを知った始めでもあった。 命 波を学んでいる先輩方がいかに謙虚で、もの静かで、全身耳となって先生のお話をうかがっているかも見えてくるようになった。聞くということ、観るということのむずかしさも少しずつ判ってきた。 「 嘘をつかない」「人にめいわくをかけない」という鉄則を毎日己に言い聞かせ、夜寝む前「本当に真実の一日だったか、どこかでごまかしたり(ついうっかりのふりを時々するが)、怠けたりしていなかったか(今でもよく怠ける)」と反省してからでないと物忘れしたような気持ちになるようにもなった。 いかにも先生らしいエピソードを一つご紹介したい。先生が16 才の頃女学校の同級生に誘われて授業をさぼって映画を見に行ったことがあったそうである。「椿姫」という映画を観ている間中どう母親に言い訳しようか考えて気もそぞろで、筋など全然わからずじまいだったとのこと。家に帰ってまっ先に母親のところに行って「お母さん、ねえ、私今日は大変だったの、お友達にさそわれて授業をさぼって映画に行ったのだけど、どうお母さんに言い訳しようか考えて考えてどうにも口実が思い浮かばなくて苦しかったのなんの。あ〜これでさっぱりした」と一息に言ったら、お母さまが「バカだねお前は」と言われたそうで、それ以来もう二度と金輪際嘘はつくまいと、その通り真っ正直に生きてこられた先生である。 嘘をつかない人は公明正大さが全身から強いオーラとなって発しているようで、後ろ暗い人には眩しく感じられるようである。よくある反応はそういう輝かしい人を避けて生きる(人生で出逢うのはろくでもない人ばかり)、憎む(陰口をきく)、いじめる(十字架にかける)、一緒にいると頭が痛くなる(今まで使っていなかった脳の部分が刺激される結果)、体がきつくて起きていられない(波動の落差で低い方が揺さぶりをかけられるショック反応)などがあると見受けられる。 また公明正大な人の存在感というものは圧倒的なもので、静かにしていてもどうせ目立つので大声を出したり着飾ったりする必要がまったくない。実際命波を学んでいる先輩方は皆もの静かで着飾らず、思い遣り深く、おしつけがましくなく、存在感がある。私は師を見るにはまず弟子を見れば良いのではないかと思う。また「教え」の真実さはそれを学んでいる人の人となりを見れば良いとも思う。 先生ほど徹底的に言うことと行うことの一致している人を私はいまでかつて見たことがない。時々あまりの律儀さにあきれかえるほどである。紙一枚、箸一本でも借りたものはきちんと傍によけておいて返す。人の持ち物は自分の横に1 年おいてあっても中を見たり使ったりはしないというふうである。 「嘘つきの行けるところは宇宙のどこにもない。何故なら宇宙は真実のみで出来ているのだから」というのが先生がよくおっしゃることばである。この意味が解るのに3年かかった。 1999.6.28 菊池静流 |