
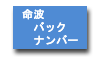
 |
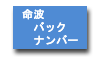
|
| 第三話「コミュニケーション脳」 | 第四話「音の心が意味」 |
 |
|
第四話
音の心が意味
私たちがコミュニケーションに使っている言葉は音が連なってできています。誰かが
「青い空がきれいですね」と言うと、あなたの脳裏には透き通った青空のイメージが浮か
び、「きれい」という感動が起こります。同じことを日本語が話せないフランスの人に言っ
たとすると、こういう反応は起きません。言語力は習得しないと意味を解することが出来
ないからです。
さて、この言葉を構築している音というものには種類があります。各言語で使用してい
る音は異なります。世界に言語はいくつあるかというと方言を数えると数えないとで三千
から一万くらいまでの差があります。この中で比較的多数の人に流通している言語の数を
約七十とした人が「七十プラス一」※と言ったことがあります。一は日本語です。それほ
ど日本語は他の言語と異なる形態を持っているということです。日本語のユニークな点は
使っている音素が少ないことと音節が全て母音で終わる開音節だということです。
ある特定の言語において意味が区別される最小の音声単位を「音素」といいますが、日
本語の音素の数が二十五個(母音五、子音二十)であるのに対し、英語では四十四個もあ
るのです。また、日本語は音素が少ないだけでなく、言葉の最小単位となる音節数も全部
で百余り※と、世界的に見てもパターンの少ない言語に分類されています。英語は一つの
母音に複数の子音がつくことで、音節数が三千以上になる複雑な言語です。音の複雑性は
フランス語やドイツ語などの印欧語族の言語全部に当てはまります。
なぜ日本語だけが開音節のみを使う言語として他に類を見ないものなのかに着目した小
田野早秧は音が一音ずつ区切れるという特徴から、もし音が連なることで出来上がった単
語の意味ではなく、音そのものに意味があるとしたら、おそらく一音ずつ区切れる言語の
中に意味が隠されているであろうと推理しました。それからもう一つのヒントは意味の意
という文字にありました。「音」という字と「心」という字が合わさって出来ていたのです。
心には意味という意味もあります。音の意味が「意」だと文字が示しているということに
も気づいたのです。そして文字は分けることでその中に隠されている新たな意味が姿を現
すということにも気づきました。
これから文字を分ける「字分け」という手法も学んでいきましょう。
※ 柴田武(編)『世界のことば小事典』大修館書店, 1993 特集「世界の言語70+1」
※ 清音五十(アイウエオ、カキ..)、濁音二十(ガギグ..ヂとヅを入れないと十八)、半
※ 濁音五(パピプ..)、ンで合計七十六(七十四)。これに拗音のキャキュキョなど十五(ヂ
※ ャ、ヂュ、ヂョを入れないと十二)と数え方は多少異なるので、百余とした。