
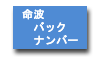
 |
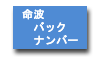
|

|
オオ脳! |
|
人間の脳は他の動物の脳とは根本的に、構造的に、量的に、そして質的に違います。 説明が少しテクニカルになりますが頭脳労働の方をよろしくお願いします。 まず大きく三つに分けると、脳幹と大脳半球と小脳になります。このうち人間と他の脊椎動物とで大きく異なるのが大脳です。ご承知のように脳には二つの半球があり、右脳と左脳と呼ばれています。間を脳梁と呼ばれる神経線維の束が連結しています。 各半球をさらに四つに区分けしたものが下図です。このような脳葉の内側にほ乳類脳と呼ばれる辺縁脳があり、その又中側に爬虫類脳と呼ばれる脳幹があります。
色は私が勝手につけたもので、実際とは関係ありません。また分布状態や各部分の大きさの比率もおおまかなもので、個人差があります。それでも四つの脳葉にまたがってあちこちに離れて分布している状況は分かると思います。 次は脳の神経細胞(ニューロンとも言います)がどう活動しているかという話です。新皮質のニューロンは比較的大きく、細胞体から出ている突起の数も多いそうで、突起は先が枝分かれしているため樹状突起を呼ばれています。また各ニューロンからは軸索と呼ばれている一本の長い神経線維の束が出ていて、これが脊椎の中まで伸びて通っています。
他にも特記すべき事項として、ニューロンの活動を補助するグリア細胞[1]の役割の重要性があります。脳を構成する細胞には二種類あって、ニューロンとその数倍から十倍もの数があるというグリア細胞です。ニューロンは増殖しません(死んだら減ったまま)が、グリア細胞は分裂して数が増えます。 アインシュタインの脳をスライスして調べた研究発表によると、シナプスのネットワークが密でしかも広範囲にまたがっているというだけでなく、高次の知的活動に関係が深いと言われる脳の39区という部分のグリア細胞の数が普通人の平均より73%も多かったという発表がされました[2]。シナプス結合が盛んに行われた結果グリア細胞が増殖したとも考えられます。 ではここで質問。高次の知的活動に不可欠なものは何でしょう。数学でも化学でも工学でも哲学でも必ず使わなければならない能力です。それは言語能力なのです。言語を使わなければこれらの研究はできません。知的活動を行っているということは言語を使っているということです。そして考える対象が何であれ、言語活動によって刺激された脳内のニューロンが情報を貯蔵するためにシナプス結合をしているのです。歳をとるに従いニューロンはシナプスも共にどんどん死んでいきます。しかしネットワークが密で広範なほど途切れた結合部分はす速く代わりの結合が穴埋めをして繋いでいくのでいわゆるボケ症状は起き難くなるということです。 これは仮説ですが、字分けという作業では前の図にあるような言語野の全てを使います。そして字が割れた時に起きる発想の転換が今まで一度も繋がったことのなかった新しい結合を形成し、結果的により広範にわたる密なニューロンのネットワークを作るかもしれません。アインシュタインのように今までだれも考えたことがなかったようなユニークな考えを構築することのできる柔軟な思考能力はシナプス結合が活発に行えるような準備が整った脳を持っていることではないかと思います。 良い作物を実らせるには良い土壌が必要なのに似ていますね。
突き詰めて受ける容器が脳。何を突き詰めるのかというと疑問の答を求めて考えぬくこと。脳は考えるためにある。考える材料は「疑問」というもの。疑問を持たなければ答を得ることは決して無い。 また月はニクヅキだから脳は肉体の部分で、しかも受け箱なら容器とも言える。そして受け入れるものは情報というコトバ。 「月」を肉体と解釈すると、「ツ」の下に「凶」がある形を凶事は肉体に付き物と解釈したい(ツという音に天鏡の文字をあてると付き物の「付」となる)。凶事は肉体に付き物。肉体がなければ災いも悩みもないですね。でもこの凶という字をよく見ると面白い形をしていることが分かります。
ついでに悩みという字は忄(リッシンベン、心の意)にツと凶。凶が付いている心は悩むと割れます。悩みたくなかったら横並びの人間同士のいざこざも地獄の沙汰にもあまり拘泥しないで視点を明るく開いた上方に向けてみましょう。 2004/08/04 |