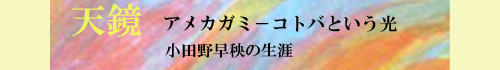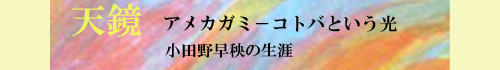『天鏡』 アメカガミ − コトバという光
|
− 小田野早秧の生涯 − 著者:菊池静流 永井迪子 装丁画:永野裕子
|
2002年夏、菊池静流が全精力を注ぎ執筆に取り組んだ一冊です。
菊池静流が抜粋した『天鏡』本文をいくつかご紹介いたします。
1 幼少期
特異性・・・・・より
独りだけ変わっているところは別に級友には気にならなかったようで、割合に人気があった。何かの遊びを始める時によくジャンケンで〈親〉ないし先攻を決めるが、そのジャンケンをする役を頼まれるのが常だった。他に面白い勉強や計算があるのに引っ張りだされるのが煩わしくて、どうにか負けてお役御免になろうと努力するのに、どうしても負けることができない。負けよう負けようと出す手がいつも勝ち手になってしまうのだ。何と一度も負けたことがないのだ。いくら何でも一度くらいは負けたでしょうと私が問うと、その憶えがないということだった。
2 青年期
五ヵ年計画・・・・・より
亡くなった母親の供養の方法だが、通常は仏壇に食物や飲み物を供え、花を飾って手を合わせるところを、死んで肉体の無くなった人に食物も飲み物も不要と考え、命そのものの糧である心やりを捧げようと思ったのである。母は信心深い人だったので、毎日お経をあげようと決めた。般若心経を選んだのは比較的短い経だということもあった。ところがその短い経を通しで上げることが出来ないのだ。たった二時間の自由時間のほうに食い込んでくる読経の時には疲れきっていて、途中で知らない間に居眠りしてしまうのだった。
そこで一計を案じた。一息で読んでしまえば眠らなくて済むと思い、呼吸を長くする方法を自己流に編み出した。その経は出来る限りの速度で読むと、百八数える間に読み終えられることを発見し、一呼吸で百八まで数える練習をした。まず肺の中の炭酸ガスの一粒までも全部吐き出し、その後に空気を取り込もうとすると横隔膜が自然に上下する。横隔膜の動きをコントロールするのが上達するほどに、数える数は大きくなっていった。目的の数に達し、一息で般若心経を読めるようになってからは読経の最中に居眠りすることはなくなった。この時培った、一息で経を読むという肺の使い方が後年他の行をするのに役立ってくることになる。余談だが、早秧が編み出した呼吸法はヨガや道教の仙道の極意で、相当の修行を積んだ行者でもなければ出来ないことだと後に人に聞かされた。
4 晩年
聖なる愚者
・包み隠さず怒り、赤裸々に生きる・・・・より
「嘘つきの行けるところは宇宙のどこにもない。何故なら宇宙は真実のみで出来ているから」とは含みの多い先生の言葉である。これをどう捉えるかが各々の人の課題だと思う。宇宙が真実だけで出来ているとしたら、宇宙ではない所とは一体どこになるのか。自分の中以外には考えられない。では自分の中とはどこか。自分の体の中というはずはないから、意識の中ということになる。嘘ばかりついている人の意識は宇宙のもつ真理すなわち、人間の都合で作られた理屈ではなく真(マコト―真言)の理(コトハリ―光透波理)によって運行されているエネルギーの場に同調できないため、行き場がないという教えであろう。
・たゆまず努力する粘着性質・・・・・・より
早秧は戦争の体験から、どうしたら人間同士が殺しあうような残酷な戦争というもののない人間社会ができるだろうかと考えた。人間同士が優しく温かい思いやりをかけあって、それぞれが天からいただいた才能を活かして助け合い、自由に生きることができる社会をどうしたら現出できるのだろう。その方法を発見するためにはまず反対に何故できないのかを突き止める必要があると考えた。人間が天という実の親(創造主)の本質である慈しみの愛に背を向け、すねたり怒ったりして、みすみす不幸になるような不合理な行為をすることの原因は根本無明、すなわち無知にある。無知なるがゆえに貪り、怒り、嫉むという執着の情に翻弄されてしまうのである。
情理というものは二律背反のように思われているが、情とは理性の裏側で、ふたつは表裏一体であということ。これを盲目的に信じる心ではなく、覚めた科学する心で追及し、納得することができなければ執着の情に翻弄され続ける人生となってしまう。では情とは何か。理とは何か。その本質を知らなければならない。その本質とは光透波であり、光透波は叡智であり、かつまた慈愛であり、さらに真空という宇宙母胎である。
|
< ご注文はメールでどうぞ。>
本の冊数×1,500円+500円(送料他)
1冊なら 2,000円
2冊なら (1,500×2)+500円=3,500円
10冊からは送料他無料です。

|