

字分けをしてみよう
2009年6月15日 6時10分
朝目覚めの直前に「飛鳥」という字を頂く。時計を見たら、6時10分。ともかくそれだけ書きとめ
て、家事などを始めた。外出する日でなにかと気ぜわしく、じっくりと座って字分けをする心の余裕が
ない。後日にしようと決めた。
同じ日の 12時6分
電車の車中で下を向いて携帯電話のメールの設定などをしていて、「ふと」窓外に目を向けた途端に
飛び込んできた看板文字がある。
「飛鳥 ドライビングスクール」 それまで窓外は全く見ていなかった。同じ文字を短期間に2回頂い
たという風に受け止めた。こういう時には字分けをする。
アスカと読んだ際に始めに脳裡に浮かんだ文字は スに対する「数」という文字だったので、まず数
値を検討する。
6(ム=務)の月の15(アルファベット15番目の文字O、これは数字のゼロでもある)、ゼロの日
の6(務)の時間の10(ト=透)分。10分は「透分」と解いた。
同じ日の12時はアルファベットのL(開くという意)と取り、6分は務(ツトメ=通透命)と取る。
天鏡図の6行目は、日本の標準語で使われている76音の中でも唯一3種類に展開している行で、
音としては、
ハヒフヘホ
バビブベボ
パピプペポ
がある。従ってそれぞれの音に関係する文字の数も多くなる。展開している世界が多いということで、
これが「務」と言うのであれば、人間にとっても天の實親にとっても為すべき仕事は多々あって忙しい
ということになる。
人間の才能には様々なものがある。それぞれの人が頂いている才能を活かして絶対透明のゼロのエネ
ルギーに通じていく務めを果たしていくことが、心にとってもっとも清々しく、快いものだと私は経験
的に知っている。持っていない才能を嘆いて、他者を羨ましく思うのは、辛い苦しいことだという経験
も嫌というほどしてきた。嫉妬は辛い。胸に突き刺さり、自己憐憫と自己嫌悪の感情に巻き込まれてし
まう。始めから持っている才能が、天から与えられた仕事、「務=ツトメ=通透明」、透明に通じる仕事
なら、楽々と、従って楽しく行える。努力の努もツトメと読むが、これの音読みは「ム」ではなく、「ド」
と読むので、他にドと読む「奴、人間という意」」「怒」とも、ちょっとしんどい感じになる。怒りが「奴
+心」という字なのも面白い。ともかく、嫌なことを無理やりして、生計を立てていけば、そりゃいろ
いろ腹が立ってきて、楽しくないことは確か。好きなことというのは大体において得意なことだと思う。
得意で、楽に上達できて、しかもそれで生活できたら楽しい人生に決まっていると思う。要は、自分が
何をする為に生まれて来たのか分かっていれば、幸せなのだと思う。言い換えれば、自分の務が分かれ
ば幸せだとなる。いずれにしても何が正解で何が間違いかは考えなくてもいいらしい。才能を備えてく
ださっている創造者側の問題だからだ。人間がすることは頂いた才能を使って出来る仕事をひたすらし
ていればいいだけ。
先日久しぶりにアメリカに行って、アメリカ人たちを久しぶりに体験。自我をむき出しにして、切磋
琢磨、自己主張も強いが、他者の主張にも眉をひそめるわけではなく、それなりに認める、要するに濁
音渦巻く世界。命波的に言えば「バビブベボを生きている」人々の社会。日本人は自我や自己主張には
少し覆いをかけて、直接ぶつからないような処世術を使って生きている人が比較的多い。「長いものに
はまかれる」し、高圧的な人にあえて立ち向かうことはせずに、一旦ひっこむ。波風はあまりたてない。
要するに比較的静かな音の社会で、音で言えば「ハヒフヘホを生きている」。ハヒフヘホと発音してみ
てください。バビブベボと比べると良く言えば穏やか、悪く言えば何かスカ抜けているような音ではな
いですか。
それはさておき、どちらの社会にも、「このままではいけない。浄化せねば」と、自己犠牲と他利主
義で生きている、「パピプペポ」の人々がいる。そのどの生き方でも、それぞれで「透明に通じる、務」
を果たそうとしているのだと今は思う。そう思えるから面白い。要するに何でもあり。
さて、飛鳥には透明(O=ゼロも透明のエネルギーの世界)と務が関係しているらしい。これを基本的
に頭に置いて、文字の検証を始めることにする。
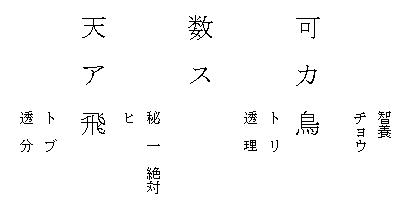 |
天の数、これは全宇宙を創造、統治、運営しているところの、精緻にして厳正なる数の法則によって
可能なものというように取った。それが絶対透明のエネルギーという智慧によって養われている宇宙の
普遍的法則である理(ことわり)の土台となっている。それは絶対性という、捉えがたくしかもあまり
にも速くて、たとえ時々片鱗か頭を掠めて飛んでいっても、すぐに消えてしまうものなのだ。捉えてじ
っくり吟味して、消化吸収し、ついには納得に繋がっていくという過程が始まらないので、いつまでも
執着の奴隷となって、苦しみながら生きていくことになる。願わくば、絶対透明の聖なるエネルギーの
一部分である自己の何たるかを知り、己の務を知り、その分を弁(わきまえ)て、そうなることで足る
を知り、悠々と生きていたいものである。

飛ぶという字は分け難い。どう分けようか考えていたら、図の梵字(注1)が脳
裡に浮かんだ。阿弥陀如来のシンボルであると言われている、サンスクリット語で
キリークという字である。良く似ている。今回は「飛」の字分けは止めにして、こ
ちらを検証することにした。勿論「飛」と同じ字ではないので、いずれはそちらも
字分けするつもりでいる。
阿弥陀はアミダと読むので。「網」と「田」の字を当てる。天網(てんもう)という電磁場の意味と
取る。これが日本語の「飛」という字になると音読みで「ヒ」と発音するので、和数字の「一」、絶対
という意味になり、また訓読みでは「トブ」と発音するので、透明の答という理の一部分とも読み解け
る。これが鳥と合わさって、アスカと読む。
キリークには、「基理空」と当てた。空(透明真空の無の世界)の方の基本的な理なので、ヒ(絶対)
トブ(透分)と整合性もある。
注1. 梵字とは・・・・古代サンスクリット語を表すインド文字のこと。一文字で神仏を表し色々な
功徳を与え、困難から救ってくれる神聖なパワーを持っています。
注2. 飛ぶ鳥と書いて何故「あすか」と読むかについて、インターネットで調べました。
http://topiarybubi.at.webry.info/200811/article_3.html
飛鳥(とぶとり)の明日香(あすか)と枕詞として使われている内に、飛鳥(とぶとり)といえば、それだけでアスカと
いう代名詞に用いられ、時間の経過とともに、飛鳥(とぶとり)がアスカと訓れるようになったと言う説があります。
“あすか”という地名のいわれについては、古墳時代から我が国に移住した、たくさんの渡来人たちが、さすら
いの果てに得た安住の地であるという意味で「安宿(あすか)」と名づけたのが転じたともいわれ、さらにその枕
詞に使われていた「飛鳥(とぶとり)」をも“あすか”と読ませることになったという説が立てられています。
地名をもって時代名としているのは、日本史上これが初めてのことです。
2009/06/18
菊池 静流